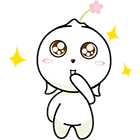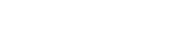文章
玲儿
2017年09月26日

シーマニアの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
春と秋は戸外の日のよく当る場所で、夏は直射日光の当たらない戸外の涼しい半日陰で、冬は日当たりのよい室内で育てます。冬の最低温度は10~15℃が目安です。
水やり
鉢土の表面が乾き始めたらたっぷりと水やりをします。水切れには弱く、すぐに下葉がしおれるので注意してください。
肥料
元肥として緩効性化成肥料を土壌に混ぜておきます。追肥は、春と秋に緩効性肥料を置き肥するか、定期的に液体肥料を施します。
病気と害虫
ホコリダニ:新芽などの柔らかい部分につきます。ハダニと異なり、ホコリダニは肉眼では見えませんが、新芽付近の節間が縮まって伸びない、新芽が茶色く変色する、ひどくなると新芽が枯れるなどの症状が見られたら、ホコリダニの可能性が高いです。適用のある殺ダニ剤で駆除します。
灰色かび病:咲き終わった花を放置すると、灰色かび病が発生することがあります。花がらはこまめに摘みましょう。

用土(鉢植え)
水はけがよく、通気性のある土が適しています。市販の草花用培養土を用いるか、赤玉土6、腐葉土4の配合土を用いるとよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
1年で鉢内がいっぱいになるので、毎年植え替えるとよいでしょう。5月から6月に、根鉢を1/3くらいくずして一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けして同じサイズの鉢に植え替えます。
ふやし方
さし芽:伸びた茎の先端を6cmほどに切って、赤玉土などにさします。鉢の中で地下茎またはランナーがたくさん伸びて芽を出すので、1本であっても根のついた地下茎やランナーを切ってさすとより確実です。
株分け:5月から6月の植え替え時に、1株に3芽以上つくように株を分けます。

主な作業
花がら摘み:花がしぼんだら、花柄のつけ根のところから切ります。こまめに花がら摘みを行わないと、灰色かび病が発生しやすくなります。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
春と秋は戸外の日のよく当る場所で、夏は直射日光の当たらない戸外の涼しい半日陰で、冬は日当たりのよい室内で育てます。冬の最低温度は10~15℃が目安です。
水やり
鉢土の表面が乾き始めたらたっぷりと水やりをします。水切れには弱く、すぐに下葉がしおれるので注意してください。
肥料
元肥として緩効性化成肥料を土壌に混ぜておきます。追肥は、春と秋に緩効性肥料を置き肥するか、定期的に液体肥料を施します。
病気と害虫
ホコリダニ:新芽などの柔らかい部分につきます。ハダニと異なり、ホコリダニは肉眼では見えませんが、新芽付近の節間が縮まって伸びない、新芽が茶色く変色する、ひどくなると新芽が枯れるなどの症状が見られたら、ホコリダニの可能性が高いです。適用のある殺ダニ剤で駆除します。
灰色かび病:咲き終わった花を放置すると、灰色かび病が発生することがあります。花がらはこまめに摘みましょう。

用土(鉢植え)
水はけがよく、通気性のある土が適しています。市販の草花用培養土を用いるか、赤玉土6、腐葉土4の配合土を用いるとよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
1年で鉢内がいっぱいになるので、毎年植え替えるとよいでしょう。5月から6月に、根鉢を1/3くらいくずして一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けして同じサイズの鉢に植え替えます。
ふやし方
さし芽:伸びた茎の先端を6cmほどに切って、赤玉土などにさします。鉢の中で地下茎またはランナーがたくさん伸びて芽を出すので、1本であっても根のついた地下茎やランナーを切ってさすとより確実です。
株分け:5月から6月の植え替え時に、1株に3芽以上つくように株を分けます。

主な作業
花がら摘み:花がしぼんだら、花柄のつけ根のところから切ります。こまめに花がら摘みを行わないと、灰色かび病が発生しやすくなります。
0
0
文章
玲儿
2017年09月26日

グロッバの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
高温多湿を好み、夏の強光線を避けた半日陰が適します。暗すぎる場所では花つきが悪くなり、軟弱に育ちます。庭植えする際は、腐葉土や堆肥などの有機物を十分すき込んでください。寒さに弱く、根茎も戸外では冬越しできないので10月中に掘り上げ、バーミキュライトなどに埋めて凍らないように室内で保管します。鉢植えの場合は地上部が枯れたら水を切り、そのまま室内で翌年の5月まで保管します。
水やり
鉢土の表面が乾いてから与えます。おう盛に生育する夏は毎日与え、水切れに十分注意します。庭植えした場合は、夏に土の表面が乾いたら水やりをしてください。

肥料
春から秋の成長期に、三要素が等量か、リン酸分がやや多めの化成肥料を置き肥として規定量施します。
病気と害虫
ナメクジの食害を受けることがあるので注意してください。
用土(鉢植え)
赤玉土小粒7、腐葉土3といった水はけのよい用土が適します。
植えつけ、 植え替え
根茎の植えつけは5月ごろが適期です。5~6号サイズの鉢に2~3球、地表から3cm程度の深さに植えます。鉢植えの植え替えも5月が適期です。生育初期に多湿、多肥にすると枯死することがあるので注意します。

ふやし方
株分け(分球):小さく分けすぎるとその後の成長が遅くなるので注意します。
主な作業
花茎切り:花がらが枯れ始めたら見苦しいので切り取ります。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
高温多湿を好み、夏の強光線を避けた半日陰が適します。暗すぎる場所では花つきが悪くなり、軟弱に育ちます。庭植えする際は、腐葉土や堆肥などの有機物を十分すき込んでください。寒さに弱く、根茎も戸外では冬越しできないので10月中に掘り上げ、バーミキュライトなどに埋めて凍らないように室内で保管します。鉢植えの場合は地上部が枯れたら水を切り、そのまま室内で翌年の5月まで保管します。
水やり
鉢土の表面が乾いてから与えます。おう盛に生育する夏は毎日与え、水切れに十分注意します。庭植えした場合は、夏に土の表面が乾いたら水やりをしてください。

肥料
春から秋の成長期に、三要素が等量か、リン酸分がやや多めの化成肥料を置き肥として規定量施します。
病気と害虫
ナメクジの食害を受けることがあるので注意してください。
用土(鉢植え)
赤玉土小粒7、腐葉土3といった水はけのよい用土が適します。
植えつけ、 植え替え
根茎の植えつけは5月ごろが適期です。5~6号サイズの鉢に2~3球、地表から3cm程度の深さに植えます。鉢植えの植え替えも5月が適期です。生育初期に多湿、多肥にすると枯死することがあるので注意します。

ふやし方
株分け(分球):小さく分けすぎるとその後の成長が遅くなるので注意します。
主な作業
花茎切り:花がらが枯れ始めたら見苦しいので切り取ります。
0
0
文章
玲儿
2017年09月25日

クルクマの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
日なたから半日陰に置くことができますが、よく日光に当てたほうが花つきがよくなり、株姿もコンパクトにまとまります。おう盛に生育する夏は土の乾燥を避け、十分な水分が必要です。根茎(棒状に肥大した球根)の掘り上げは10月中に行い、バーミキュライトなどに埋めて凍らないように注意し、翌年の5月まで室内で保管します。根茎も寒さに弱いため、戸外で植えたままにすると枯れてしまうので注意します。

水やり
鉢土の表面が乾いてから水を与えてください。生育期は乾燥を嫌うので、夏に日当たりのよい場所で管理する場合は毎日与えます。特に高温乾燥が激しい場合には朝夕1日2回、水やりをするとよいでしょう。
庭植えした場合は、夏に土の表面が乾いたら水やりをします。
肥料
春から秋の成長期に、三要素が等量か、リン酸分がやや多めの化成肥料を置き肥として規定量施します。よく開花しているときは肥料を多く必要とするので、液体肥料も併用して施します。開花期間が長いので、肥料切れに注意してください。

病気と害虫
病害虫の心配は特にありません。
用土(鉢植え)
赤玉土小粒7、腐葉土3といった水はけのよい用土が適しますが、市販の培養土を使ってもよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
根茎を植えつけるのは5月の大型連休過ぎごろが適期です。5~6号サイズの深さのある腰高鉢などを用い、地表から3㎝程度の深さに1球植えつけます。生育初期に多湿、多肥にすると枯死することがあるので注意します。

ふやし方
株分け(分球):大きく育った根茎を分けてふやすことができます。根が伸びた先のイモ状にふくらんだ部分に養分を蓄えるので、分ける際はイモ状の部分をとらないように注意してください。
主な作業
花茎切り:花後は咲き終えた花茎を切り戻します。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
日なたから半日陰に置くことができますが、よく日光に当てたほうが花つきがよくなり、株姿もコンパクトにまとまります。おう盛に生育する夏は土の乾燥を避け、十分な水分が必要です。根茎(棒状に肥大した球根)の掘り上げは10月中に行い、バーミキュライトなどに埋めて凍らないように注意し、翌年の5月まで室内で保管します。根茎も寒さに弱いため、戸外で植えたままにすると枯れてしまうので注意します。

水やり
鉢土の表面が乾いてから水を与えてください。生育期は乾燥を嫌うので、夏に日当たりのよい場所で管理する場合は毎日与えます。特に高温乾燥が激しい場合には朝夕1日2回、水やりをするとよいでしょう。
庭植えした場合は、夏に土の表面が乾いたら水やりをします。
肥料
春から秋の成長期に、三要素が等量か、リン酸分がやや多めの化成肥料を置き肥として規定量施します。よく開花しているときは肥料を多く必要とするので、液体肥料も併用して施します。開花期間が長いので、肥料切れに注意してください。

病気と害虫
病害虫の心配は特にありません。
用土(鉢植え)
赤玉土小粒7、腐葉土3といった水はけのよい用土が適しますが、市販の培養土を使ってもよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
根茎を植えつけるのは5月の大型連休過ぎごろが適期です。5~6号サイズの深さのある腰高鉢などを用い、地表から3㎝程度の深さに1球植えつけます。生育初期に多湿、多肥にすると枯死することがあるので注意します。

ふやし方
株分け(分球):大きく育った根茎を分けてふやすことができます。根が伸びた先のイモ状にふくらんだ部分に養分を蓄えるので、分ける際はイモ状の部分をとらないように注意してください。
主な作業
花茎切り:花後は咲き終えた花茎を切り戻します。
0
0
文章
玲儿
2017年09月25日

グラジオラス(夏咲き)の育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
日当たりのよいことが大切な条件です。少なくとも半日くらいは日光が当たらないと、花が咲きにくくなります。最低温度15℃以上、日中は25℃以上で生育が活発になりますが、これより低くても生育は可能です。球根の植えつけは、霜や凍結の心配がなくなってから、3月下旬以降が適期で、7月まで順次時期をずらして植えることができます。植えてから咲くまで約3~4か月、木子からでは5か月くらいかかります。本葉が2枚展開したころから球根の中に花芽(蕾のもと)がつくられるため、この時期からの低温、低日照、極端な乾燥は、花がきれいに咲かない原因となりますから注意が必要です。

水やり
乾燥には強いのですが、成長期には十分な水分を必要とします。庭植えでは、バークチップなどでマルチングをするか、丈の低い草花を株元に植えるのもよい方法です。鉢植えは、本葉が出てから開花まで、土の表面が乾いたらたっぷり水を与えます。開花後はやや乾かし気味にしてもかまいません。
肥料
比較的やせ地でもよく育ちます。庭植えは、元肥と開花後にお礼肥を施します。鉢植えは、元肥のほか、葉が茂っている間、月に1回置き肥を施すか、月に3回くらい液体肥料を施します。いずれもチッ素分はやや少なく、リン酸、カリ分の多いものが適します。

病気と害虫
病気:首腐病、ウイルス病など
肥料分、特にチッ素が多いと球根が腐りやすくなります。また、連作すると、首腐病などの病気が出やすくなりますから、2~3年で植え場所を変え、鉢植えは毎年新しい用土を使うようにします。ウイルス病の発生した株は処分します。
害虫:ハダニ
ハダニがつきやすいので、水で洗い流すとよいでしょう。
用土(鉢植え)
庭植えでは、堆肥や腐葉土を混ぜ、土壌をよくして植えつけます。鉢植えは、赤玉土7、腐葉土3の配合土や、一般の草花用培養土など、水はけのよいものであれば、土質はあまり選びませんが、少量の苦土石灰を混ぜておくとよいでしょう。

植えつけ、 植え替え
球根の高さの2倍くらいの土がかぶさるような深さに植えます。間隔は10cm以上あけます。丸みと厚みのある球根がよい球根で、扁平なものはよくありません。木子は直径1cm以上あれば十分開花します。大きな球根は2つに切り分けて、切り口に石灰などをつけて植えるのもよい方法です。
ふやし方
分球:新球の回りにたくさんの木子ができるので、必要な分をとっておきます。
タネまき:タネも実ります。これをまくと、3年目には花が咲くようになりますが、元の親と異なる花が咲くことも多くあります。

主な作業
土寄せ、支柱立て:花が咲くと倒れやすいので、蕾が伸びてきたら、根元に土を寄せるか、または支柱を立てておきます。蕾は成長するので、支柱との結び目には注意します。
球根の掘り上げ、貯蔵:秋に葉が枯れてきたら株を掘り上げて日陰で乾燥させます。完全に乾いてから茎葉を切り取り、球根の選別を行います。春に植えたときの球根はしなびて枯れているので取り除き、木子も取り外して別々にし、冬期は凍らないところで貯蔵します。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
日当たりのよいことが大切な条件です。少なくとも半日くらいは日光が当たらないと、花が咲きにくくなります。最低温度15℃以上、日中は25℃以上で生育が活発になりますが、これより低くても生育は可能です。球根の植えつけは、霜や凍結の心配がなくなってから、3月下旬以降が適期で、7月まで順次時期をずらして植えることができます。植えてから咲くまで約3~4か月、木子からでは5か月くらいかかります。本葉が2枚展開したころから球根の中に花芽(蕾のもと)がつくられるため、この時期からの低温、低日照、極端な乾燥は、花がきれいに咲かない原因となりますから注意が必要です。

水やり
乾燥には強いのですが、成長期には十分な水分を必要とします。庭植えでは、バークチップなどでマルチングをするか、丈の低い草花を株元に植えるのもよい方法です。鉢植えは、本葉が出てから開花まで、土の表面が乾いたらたっぷり水を与えます。開花後はやや乾かし気味にしてもかまいません。
肥料
比較的やせ地でもよく育ちます。庭植えは、元肥と開花後にお礼肥を施します。鉢植えは、元肥のほか、葉が茂っている間、月に1回置き肥を施すか、月に3回くらい液体肥料を施します。いずれもチッ素分はやや少なく、リン酸、カリ分の多いものが適します。

病気と害虫
病気:首腐病、ウイルス病など
肥料分、特にチッ素が多いと球根が腐りやすくなります。また、連作すると、首腐病などの病気が出やすくなりますから、2~3年で植え場所を変え、鉢植えは毎年新しい用土を使うようにします。ウイルス病の発生した株は処分します。
害虫:ハダニ
ハダニがつきやすいので、水で洗い流すとよいでしょう。
用土(鉢植え)
庭植えでは、堆肥や腐葉土を混ぜ、土壌をよくして植えつけます。鉢植えは、赤玉土7、腐葉土3の配合土や、一般の草花用培養土など、水はけのよいものであれば、土質はあまり選びませんが、少量の苦土石灰を混ぜておくとよいでしょう。

植えつけ、 植え替え
球根の高さの2倍くらいの土がかぶさるような深さに植えます。間隔は10cm以上あけます。丸みと厚みのある球根がよい球根で、扁平なものはよくありません。木子は直径1cm以上あれば十分開花します。大きな球根は2つに切り分けて、切り口に石灰などをつけて植えるのもよい方法です。
ふやし方
分球:新球の回りにたくさんの木子ができるので、必要な分をとっておきます。
タネまき:タネも実ります。これをまくと、3年目には花が咲くようになりますが、元の親と異なる花が咲くことも多くあります。

主な作業
土寄せ、支柱立て:花が咲くと倒れやすいので、蕾が伸びてきたら、根元に土を寄せるか、または支柱を立てておきます。蕾は成長するので、支柱との結び目には注意します。
球根の掘り上げ、貯蔵:秋に葉が枯れてきたら株を掘り上げて日陰で乾燥させます。完全に乾いてから茎葉を切り取り、球根の選別を行います。春に植えたときの球根はしなびて枯れているので取り除き、木子も取り外して別々にし、冬期は凍らないところで貯蔵します。
0
0
文章
玲儿
2017年09月25日

ウラシマソウの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
年間を通して日陰を好み、日ざしが強いとすぐに葉が傷みます。
芽出しから開花までは30~50%の遮光で明るい日陰をつくり、ゆったりと花を咲かせます。花後は50~75%の遮光下、真夏は75%以上の遮光下か棚下などの日が当たらない場所で管理し、葉の傷みや葉焼けを防ぎます。秋に入るとほとんどは葉を落として休眠に入ります。冬の凍結を嫌うので、そのまま棚下で管理するか、ハウスの暗い場所へ移して春まで休眠させましょう。
水やり
年間を通して乾燥を嫌います。毎日たっぷりと水を与えましょう。葉が大きく茂るころからは、上から水をかけると水の重みで茎が折れることがよくあります。茎に支柱などを立てるか、株元から水やりをするとよいでしょう。休眠中も多少の湿り気があるほうがよいので、少し乾いてきたら水やりをします。

肥料
植えつけ、植え替え時に元肥を一つまみ入れます。
生育中は肥料を好みます。葉が開く4月下旬ごろに置き肥をします。また、このころから葉が枯れ始めるまで、チッ素、リン酸、カリが等量の液体肥料を2週間に1回施すと効果的です。
病気と害虫
病気:軟腐病、白絹病
地上部が突然枯れて球根が腐る軟腐病や白絹病に注意してください。
害虫:ネグサレセンチュウ、コナカイガラムシ(ネカイガラムシ)、コナアブラムシ(ネアブラムシ)、ナメクジ、イモムシ、ネズミなど
地下部に発生する害虫としては、球根を腐敗させるネグサレセンチュウ、球根に白い粒がたくさんつくコナカイガラムシ(ネカイガラムシ)やコナアブラムシ(ネアブラムシ)があります。冬の間はネズミに食害されることもあります。
地上部は、特に芽出しのころにナメクジやイモムシに食害されます。ハウス栽培ではアブラムシやコナジラミ、ハダニなどにも注意します。
用土(鉢植え)
鉢は特に選びませんが、中深鉢以上の深さで、やや硬めのものや釉薬(うわぐすり)がかかった乾きにくいものがよいでしょう。
乾燥を嫌いますが、常に多湿状態でもよくありません。一般的な赤玉土を主体に鹿沼土などを、水やりの加減に合わせて5:5か6:4に配合するとよいでしょう。凍結で用土がくずれやすい地域では軽石を1割ほど混入してもよいでしょう。

植えつけ、 植え替え
植えつけは基本的には休眠中に行います。球根は植える前に水洗いして、古い皮や汚れた部分を落とします。植える深さは、芽の先端が2~3cm埋まる程度がよいでしょう。植え込み後の鉢は、冬に凍結しない場所で管理します。
鉢植えの植え替えは毎年行うと理想的です。植えつけと同様に休眠中に作業します。
ふやし方
分球:親球根のまわりにできた小さな球根を、無理に外さず、自然に外れているものを植えつけます。ただし、翌年すぐに芽が出ないものも多くあります。とりあえずは親球根のまわりに植え込んで、大きくなったら別の鉢に植え替えます。
タネまき:結実した果実は、11月下旬から12月ごろに完熟して赤くなります。花茎が倒れたら、果実をとって1粒ずつ水洗いします。中から白褐色の球根状のタネが出てくるので、これを培養土にとりまきします。ただし、ウラシマソウは発芽まで2年かかります。発芽後も成長は遅く、開花まで早くても5年を要します。
主な作業
交配:開花3日後から1週間以内に、仏炎苞を破いて肉穂花序をむき出しにします。このとき、花粉が出ていれば雄花、先端が突起になり、つやがあれば雌花です。綿棒などで雄花の花粉をつけて、雌花の先端をポンポンとたたけば完了です。その後は2週間ほど水やりなどで花に水をかけないように注意します。結実したら成功です。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
年間を通して日陰を好み、日ざしが強いとすぐに葉が傷みます。
芽出しから開花までは30~50%の遮光で明るい日陰をつくり、ゆったりと花を咲かせます。花後は50~75%の遮光下、真夏は75%以上の遮光下か棚下などの日が当たらない場所で管理し、葉の傷みや葉焼けを防ぎます。秋に入るとほとんどは葉を落として休眠に入ります。冬の凍結を嫌うので、そのまま棚下で管理するか、ハウスの暗い場所へ移して春まで休眠させましょう。
水やり
年間を通して乾燥を嫌います。毎日たっぷりと水を与えましょう。葉が大きく茂るころからは、上から水をかけると水の重みで茎が折れることがよくあります。茎に支柱などを立てるか、株元から水やりをするとよいでしょう。休眠中も多少の湿り気があるほうがよいので、少し乾いてきたら水やりをします。

肥料
植えつけ、植え替え時に元肥を一つまみ入れます。
生育中は肥料を好みます。葉が開く4月下旬ごろに置き肥をします。また、このころから葉が枯れ始めるまで、チッ素、リン酸、カリが等量の液体肥料を2週間に1回施すと効果的です。
病気と害虫
病気:軟腐病、白絹病
地上部が突然枯れて球根が腐る軟腐病や白絹病に注意してください。
害虫:ネグサレセンチュウ、コナカイガラムシ(ネカイガラムシ)、コナアブラムシ(ネアブラムシ)、ナメクジ、イモムシ、ネズミなど
地下部に発生する害虫としては、球根を腐敗させるネグサレセンチュウ、球根に白い粒がたくさんつくコナカイガラムシ(ネカイガラムシ)やコナアブラムシ(ネアブラムシ)があります。冬の間はネズミに食害されることもあります。
地上部は、特に芽出しのころにナメクジやイモムシに食害されます。ハウス栽培ではアブラムシやコナジラミ、ハダニなどにも注意します。
用土(鉢植え)
鉢は特に選びませんが、中深鉢以上の深さで、やや硬めのものや釉薬(うわぐすり)がかかった乾きにくいものがよいでしょう。
乾燥を嫌いますが、常に多湿状態でもよくありません。一般的な赤玉土を主体に鹿沼土などを、水やりの加減に合わせて5:5か6:4に配合するとよいでしょう。凍結で用土がくずれやすい地域では軽石を1割ほど混入してもよいでしょう。

植えつけ、 植え替え
植えつけは基本的には休眠中に行います。球根は植える前に水洗いして、古い皮や汚れた部分を落とします。植える深さは、芽の先端が2~3cm埋まる程度がよいでしょう。植え込み後の鉢は、冬に凍結しない場所で管理します。
鉢植えの植え替えは毎年行うと理想的です。植えつけと同様に休眠中に作業します。
ふやし方
分球:親球根のまわりにできた小さな球根を、無理に外さず、自然に外れているものを植えつけます。ただし、翌年すぐに芽が出ないものも多くあります。とりあえずは親球根のまわりに植え込んで、大きくなったら別の鉢に植え替えます。
タネまき:結実した果実は、11月下旬から12月ごろに完熟して赤くなります。花茎が倒れたら、果実をとって1粒ずつ水洗いします。中から白褐色の球根状のタネが出てくるので、これを培養土にとりまきします。ただし、ウラシマソウは発芽まで2年かかります。発芽後も成長は遅く、開花まで早くても5年を要します。
主な作業
交配:開花3日後から1週間以内に、仏炎苞を破いて肉穂花序をむき出しにします。このとき、花粉が出ていれば雄花、先端が突起になり、つやがあれば雌花です。綿棒などで雄花の花粉をつけて、雌花の先端をポンポンとたたけば完了です。その後は2週間ほど水やりなどで花に水をかけないように注意します。結実したら成功です。
0
0
文章
玲儿
2017年09月25日

プテロスティリスの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
多くの洋ランと同じ置き場でよく、秋と春は40%遮光程度の日光がよく当たる場所に置きます。冬は、ガラス越しの日光が当たる室内に置いて管理しましょう。生育中の地上部は蒸れを嫌うので、狭い空間に置いて蒸れないように注意します。夏は地下部の球根を掘り上げ、乾燥しない状態を保ちながら冷暗所で保管します。
水やり
植え込み材料が乾かないように、水を十分与えることが必要です。生育期間中は、常に新鮮な水を与え続けましょう。
肥料
生育期間の10月から1月ごろの間は、規定倍率の2倍ぐらいに薄めた液体肥料を週1回程度施します。
病気と害虫
病気:特にありません。
害虫:ナメクジ
特にありませんが、ナメクジの食害に注意し、発見しだい捕殺します。
用土(鉢植え)
水はけがよく、かつ保水性のあるやや細かな砂質の用土を使用します。川砂と鹿沼土などの微粒を混ぜて使ってもよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
夏が終わるころ、底穴が多く水はけがよいプラスチック鉢に植えつけます。あまり深植えしないように注意し、バルブ1個分の深さを目安に植え込みます。
ふやし方
数年にわたって栽培すると、地下の球根(バルブ)がふえてくるので、これを分球し、ふやすことが可能です。
主な作業
春から初夏にかけて地上部が枯れたら、球根(バルブ)を掘り上げ、乾燥を防ぐために水ゴケなどで軽く包み、秋まで冷暗所で保管します。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
多くの洋ランと同じ置き場でよく、秋と春は40%遮光程度の日光がよく当たる場所に置きます。冬は、ガラス越しの日光が当たる室内に置いて管理しましょう。生育中の地上部は蒸れを嫌うので、狭い空間に置いて蒸れないように注意します。夏は地下部の球根を掘り上げ、乾燥しない状態を保ちながら冷暗所で保管します。
水やり
植え込み材料が乾かないように、水を十分与えることが必要です。生育期間中は、常に新鮮な水を与え続けましょう。
肥料
生育期間の10月から1月ごろの間は、規定倍率の2倍ぐらいに薄めた液体肥料を週1回程度施します。
病気と害虫
病気:特にありません。
害虫:ナメクジ
特にありませんが、ナメクジの食害に注意し、発見しだい捕殺します。
用土(鉢植え)
水はけがよく、かつ保水性のあるやや細かな砂質の用土を使用します。川砂と鹿沼土などの微粒を混ぜて使ってもよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
夏が終わるころ、底穴が多く水はけがよいプラスチック鉢に植えつけます。あまり深植えしないように注意し、バルブ1個分の深さを目安に植え込みます。
ふやし方
数年にわたって栽培すると、地下の球根(バルブ)がふえてくるので、これを分球し、ふやすことが可能です。
主な作業
春から初夏にかけて地上部が枯れたら、球根(バルブ)を掘り上げ、乾燥を防ぐために水ゴケなどで軽く包み、秋まで冷暗所で保管します。
0
0
文章
小九
2017年09月25日

一、#白粉病 的危害

白粉病主要危害枸杞叶片,叶面覆满白色霉斑(初期)和粉斑(稍后),严重时枸杞植株外呈现一片白色,使叶片光合作用受阻,终致叶片变黄,易脱落。
二、白粉病的发病条件
病菌以菌丝体或分生孢子在枸杞的枯枝残叶或随病果遗落在土中越冬,翌年春季开始萌动,在枸杞开花及幼果期侵染引起发病。高温多雨年份、土壤湿度大、空气潮湿、土壤缺肥、植株衰弱易发病。天气干燥比多雨天气发病重,日夜温差大有利于此病的发生、蔓延。

三、预防与治理方案
1、田园管理:冬季做好田园清洁,清扫地表病叶、枯枝,除去带菌病枝,减少初侵染源。清除病叶和病果,集中深埋或烧毁,以减少菌源。
2、药物预防:在病害常发期前,使用靓果安作为保护药剂,按400-600倍液进行喷施。
重点防治时期:花期、幼果期。
3、药物治疗:轻微发病时,速净按300—500倍液稀释喷施,5—7天用药1次;病情严重时,按300倍液稀释喷施,3天用药1次,喷药次数视病情而定。

白粉病主要危害枸杞叶片,叶面覆满白色霉斑(初期)和粉斑(稍后),严重时枸杞植株外呈现一片白色,使叶片光合作用受阻,终致叶片变黄,易脱落。
二、白粉病的发病条件
病菌以菌丝体或分生孢子在枸杞的枯枝残叶或随病果遗落在土中越冬,翌年春季开始萌动,在枸杞开花及幼果期侵染引起发病。高温多雨年份、土壤湿度大、空气潮湿、土壤缺肥、植株衰弱易发病。天气干燥比多雨天气发病重,日夜温差大有利于此病的发生、蔓延。

三、预防与治理方案
1、田园管理:冬季做好田园清洁,清扫地表病叶、枯枝,除去带菌病枝,减少初侵染源。清除病叶和病果,集中深埋或烧毁,以减少菌源。
2、药物预防:在病害常发期前,使用靓果安作为保护药剂,按400-600倍液进行喷施。
重点防治时期:花期、幼果期。
3、药物治疗:轻微发病时,速净按300—500倍液稀释喷施,5—7天用药1次;病情严重时,按300倍液稀释喷施,3天用药1次,喷药次数视病情而定。
0
1
文章
小九
2017年09月25日

#柠檬 树长虫子了,可恶的虫子几乎把柠檬的叶子吃光了,抓了虫不出半个月又出来了啃叶子了,它们到底躲在什么地方,有什么办法根治吗?
小九想说的是,病虫害防治要采用农业防治、生物防治和药剂防治等综合方法把病源、虫源控制在最低水平:
1、农业防治:
增施农家肥,增强树体的抵抗力,勤除杂草清洁园地,消灭病虫寄主,勤修剪枯枝、病枝、虫枝,以防病虫蔓延。
2、生物防治:
果园养鸡、鸭、蜂有一定防治效果。
3、药剂防治:
以防为主,以治为辅,了解病情、掌握虫情,看准时期,对症下药。各大片区要统一喷药防治,农药要轮换使用。
当然,见效最快治理方法最好的当然是根据柠檬树的病虫害来对症下药啦,具体的问题还是需要具体分析的,根据不同的病虫害采取不同的防治方法才是最好的选择,下面花匠大叔可以为您介绍一下柠檬树常见的虫害及其防治方法:
1、柠檬蚧壳虫
危害与发生:树枝密集、互相荫蔽的果园容易发生蚧壳虫,蚧壳虫主要集中在叶背、果实表面吸汁,虫体颜色有红褐色、白色、黑色等,形状有圆形、点形、棉花形状等,多种蚧壳虫发生的果园,煤烟病比较严重。
防治方法:①合理修剪,保持果树通风透气。②注意虫害发生初期防治,在每年的3—5月预防最好,可选用噻嗪酮600—800倍、速扑杀1000—1500倍、石硫合剂300倍。
2、柠檬蚜虫、粉虱
危害与发生:在柠檬新梢、新叶抽出后,蚜虫集中在叶背吸汁,造成新叶卷起,不能正常生长,蚜虫常见颜色为深绿色、黑色,蚜虫发生危害时,常有蚂蚁出现和煤烟病发生,粉虱的发生也是在新梢、新叶抽出后,喜欢在嫩叶背面吸汁,惊动易飞,会造成叶片发育不良,大量发生时引起煤烟病爆发,粉虱有白粉虱和黑刺粉虱两种,成虫喜阴暗,迁飞能力强,常在树冠内部幼嫩叶边产卵,卵成白色小粒状。
防治方法:①合理修剪,保持果树通风透气,合理出芽留梢,避免粉虱、蚜虫的发生。②合理选用农药,在蚜虫、粉虱发生时可选用下列农药喷施:好年冬1000倍,70%吡虫啉2000—2500倍,万灵2000倍,啶虫咪1000—1500倍,1.8%阿维菌素2000倍。
3、柠檬潜叶蛾
危害与发生:潜叶蛾是柠檬苗木、幼树和成年树嫩梢的重要害虫,以幼虫为害新梢嫩叶,潜入嫩叶表皮下取食叶肉,形成银白色弯曲的隧道,在中央形成一条黑线,由于虫道蜿蜒曲折,导致新叶卷缩,硬化,叶片脱落,春、夏、秋梢发生严重,叶片受害后会引起溃疡病的发生,该虫又叫画图虫、鬼画符。
防治方法:①合理控梢放芽,统一放梢,切断害虫食物链。②新梢出1—2cm时,每隔7天喷药一次至梢停为止,使用农药有:三氟氯氰菊脂3000—3500倍,万灵2000—2500倍,阿维菌素2500—3000倍,克蛾宝2000—2500倍,防治成虫应在傍晚喷药,潜入叶内的幼虫应在午后喷药。
4、柠檬红蜘蛛
为害与发生:红蜘蛛以成螨和若螨在树冠外膛,用口器刺破叶片、嫩梢及果实的表皮,吮吸汁液,受害叶片表面呈现许多密集白点,叶片失绿,失去光泽,严重时整树叶变灰白,引起落叶,红蜘蛛一年发生15—20代,世代重叠,此虫喜光,故树冠上层枝叶虫只密度较大,以春秋两季发生最为严重。红蜘蛛大小如针眼,色暗红。
防治方法:①检查虫情,螨卵3—4头时应及时防治。②冬季清园喷1.5—2度石硫合剂+敌百虫+尼索郎,以起到长期预防作用。③农药防治:在每次红蜘蛛发生时(2—3头)应用1.8%阿维菌素2000—3000倍,螨园清1200—1500倍,灭扫利2000—3000,73%炔螨特2000—3000倍。
5、柠檬锈壁虱
为害与发生:锈壁虱喜荫蔽,在树冠内以成螨、若螨群集果面、叶片及嫩梢上为害,刺破表皮细胞,吮吸汁液,果实被害后,皮变黑褐色,粗糙,俗称麻果、黑皮果,严重时引起落叶,一年发生15—20代,世代重叠,春季发生最为严重。
防治方法:①检查虫情,在幼果有白色小粉点时防治。②在锈壁虱发生时选下列农药喷施:1.8%阿维菌素2000—3000倍,螨园清1200—1500倍,灭扫利2000—3000,73%炔螨特2000—3000倍。
小九想说的是,病虫害防治要采用农业防治、生物防治和药剂防治等综合方法把病源、虫源控制在最低水平:
1、农业防治:
增施农家肥,增强树体的抵抗力,勤除杂草清洁园地,消灭病虫寄主,勤修剪枯枝、病枝、虫枝,以防病虫蔓延。
2、生物防治:
果园养鸡、鸭、蜂有一定防治效果。
3、药剂防治:
以防为主,以治为辅,了解病情、掌握虫情,看准时期,对症下药。各大片区要统一喷药防治,农药要轮换使用。
当然,见效最快治理方法最好的当然是根据柠檬树的病虫害来对症下药啦,具体的问题还是需要具体分析的,根据不同的病虫害采取不同的防治方法才是最好的选择,下面花匠大叔可以为您介绍一下柠檬树常见的虫害及其防治方法:
1、柠檬蚧壳虫
危害与发生:树枝密集、互相荫蔽的果园容易发生蚧壳虫,蚧壳虫主要集中在叶背、果实表面吸汁,虫体颜色有红褐色、白色、黑色等,形状有圆形、点形、棉花形状等,多种蚧壳虫发生的果园,煤烟病比较严重。
防治方法:①合理修剪,保持果树通风透气。②注意虫害发生初期防治,在每年的3—5月预防最好,可选用噻嗪酮600—800倍、速扑杀1000—1500倍、石硫合剂300倍。
2、柠檬蚜虫、粉虱
危害与发生:在柠檬新梢、新叶抽出后,蚜虫集中在叶背吸汁,造成新叶卷起,不能正常生长,蚜虫常见颜色为深绿色、黑色,蚜虫发生危害时,常有蚂蚁出现和煤烟病发生,粉虱的发生也是在新梢、新叶抽出后,喜欢在嫩叶背面吸汁,惊动易飞,会造成叶片发育不良,大量发生时引起煤烟病爆发,粉虱有白粉虱和黑刺粉虱两种,成虫喜阴暗,迁飞能力强,常在树冠内部幼嫩叶边产卵,卵成白色小粒状。
防治方法:①合理修剪,保持果树通风透气,合理出芽留梢,避免粉虱、蚜虫的发生。②合理选用农药,在蚜虫、粉虱发生时可选用下列农药喷施:好年冬1000倍,70%吡虫啉2000—2500倍,万灵2000倍,啶虫咪1000—1500倍,1.8%阿维菌素2000倍。
3、柠檬潜叶蛾
危害与发生:潜叶蛾是柠檬苗木、幼树和成年树嫩梢的重要害虫,以幼虫为害新梢嫩叶,潜入嫩叶表皮下取食叶肉,形成银白色弯曲的隧道,在中央形成一条黑线,由于虫道蜿蜒曲折,导致新叶卷缩,硬化,叶片脱落,春、夏、秋梢发生严重,叶片受害后会引起溃疡病的发生,该虫又叫画图虫、鬼画符。
防治方法:①合理控梢放芽,统一放梢,切断害虫食物链。②新梢出1—2cm时,每隔7天喷药一次至梢停为止,使用农药有:三氟氯氰菊脂3000—3500倍,万灵2000—2500倍,阿维菌素2500—3000倍,克蛾宝2000—2500倍,防治成虫应在傍晚喷药,潜入叶内的幼虫应在午后喷药。
4、柠檬红蜘蛛
为害与发生:红蜘蛛以成螨和若螨在树冠外膛,用口器刺破叶片、嫩梢及果实的表皮,吮吸汁液,受害叶片表面呈现许多密集白点,叶片失绿,失去光泽,严重时整树叶变灰白,引起落叶,红蜘蛛一年发生15—20代,世代重叠,此虫喜光,故树冠上层枝叶虫只密度较大,以春秋两季发生最为严重。红蜘蛛大小如针眼,色暗红。
防治方法:①检查虫情,螨卵3—4头时应及时防治。②冬季清园喷1.5—2度石硫合剂+敌百虫+尼索郎,以起到长期预防作用。③农药防治:在每次红蜘蛛发生时(2—3头)应用1.8%阿维菌素2000—3000倍,螨园清1200—1500倍,灭扫利2000—3000,73%炔螨特2000—3000倍。
5、柠檬锈壁虱
为害与发生:锈壁虱喜荫蔽,在树冠内以成螨、若螨群集果面、叶片及嫩梢上为害,刺破表皮细胞,吮吸汁液,果实被害后,皮变黑褐色,粗糙,俗称麻果、黑皮果,严重时引起落叶,一年发生15—20代,世代重叠,春季发生最为严重。
防治方法:①检查虫情,在幼果有白色小粉点时防治。②在锈壁虱发生时选下列农药喷施:1.8%阿维菌素2000—3000倍,螨园清1200—1500倍,灭扫利2000—3000,73%炔螨特2000—3000倍。
0
1
文章
玲儿
2017年09月24日

パフィオペディラムの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
強い日光は好まないランなので、ほぼ一年中日よけをしながら栽培します。冬は窓辺のレースのカーテン越し、梅雨明け後の夏は戸外に出し50%程度の遮光の下で管理します。戸外で長雨に当たると腐ることがあるので注意しましょう。常に風に当たるようにすると元気に育ちます。
水やり
植え込み材料が1年を通してやや湿っている状態に保ちます。夏場の生育おう盛な時期は、水をやや多く与えるようにします。

肥料
液体肥料を中心に施しますが、根への負担を減らすため基準の倍率よりも1.5~2倍程度薄くして施します。緩効性化成肥料や有機質肥料を施してもかまいませんが、施す量は控えめにします。
病気と害虫
病気:軟腐病
換気が悪いと株元によく発生し、あめ色状になり腐ります。風通しをよくし、株の間隔をあけて予防しましょう。腐り始めた葉はつけ根からていねいに取り除き、その後はしばらく乾かし気味にしておきます。

害虫:カイガラムシ
カイガラムシは葉の中心部に入り込み、株を衰弱させます。ふだんは目につかなくても、花芽が伸びてくると白いカイガラムシが一緒に出てくることがあります。
用土(鉢植え)
水はけがよく、かつ鉢内が適度に湿り気をもつ植え込み材料を好みます。主に細かなバークと軽石を混合したものを使いますが、水ゴケでもよく育ちます。
植えつけ、 植え替え
植え替えは1年おきに、春に行います。根があまり多くないので、折らないようにていねいに古い植え込み材料を取り除き、新しい植え込み材料で植え込みます。

ふやし方
株分けでふやします。春中ごろに行い、あまり小さく分けないように注意しましょう。
主な作業
支柱立て:花芽が伸びてきたら、支柱を立てて花茎を支えます。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
強い日光は好まないランなので、ほぼ一年中日よけをしながら栽培します。冬は窓辺のレースのカーテン越し、梅雨明け後の夏は戸外に出し50%程度の遮光の下で管理します。戸外で長雨に当たると腐ることがあるので注意しましょう。常に風に当たるようにすると元気に育ちます。
水やり
植え込み材料が1年を通してやや湿っている状態に保ちます。夏場の生育おう盛な時期は、水をやや多く与えるようにします。

肥料
液体肥料を中心に施しますが、根への負担を減らすため基準の倍率よりも1.5~2倍程度薄くして施します。緩効性化成肥料や有機質肥料を施してもかまいませんが、施す量は控えめにします。
病気と害虫
病気:軟腐病
換気が悪いと株元によく発生し、あめ色状になり腐ります。風通しをよくし、株の間隔をあけて予防しましょう。腐り始めた葉はつけ根からていねいに取り除き、その後はしばらく乾かし気味にしておきます。

害虫:カイガラムシ
カイガラムシは葉の中心部に入り込み、株を衰弱させます。ふだんは目につかなくても、花芽が伸びてくると白いカイガラムシが一緒に出てくることがあります。
用土(鉢植え)
水はけがよく、かつ鉢内が適度に湿り気をもつ植え込み材料を好みます。主に細かなバークと軽石を混合したものを使いますが、水ゴケでもよく育ちます。
植えつけ、 植え替え
植え替えは1年おきに、春に行います。根があまり多くないので、折らないようにていねいに古い植え込み材料を取り除き、新しい植え込み材料で植え込みます。

ふやし方
株分けでふやします。春中ごろに行い、あまり小さく分けないように注意しましょう。
主な作業
支柱立て:花芽が伸びてきたら、支柱を立てて花茎を支えます。
0
0
文章
玲儿
2017年09月24日

ディサの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
一年中、日光を非常に好みますが、夏の高温は苦手です。そのため、夏は日当たりがよくても高温にならない環境をつくらないかぎり、ディサの栽培はできません。
寒さについては、10℃を下回っても大丈夫ですが、極端な低温では株が傷みます。
また、新鮮な風に当たるとよく育ちます。閉めきった環境の場合は、常に換気扇などを回し、空気を循環させる必要があります。

水やり
新鮮で冷たい水を常に与えます。水道水のくみ置き水では、うまく育ちません。山の急流を流れるような、不純物が少なく、手を入れられないぐらい冷たい水を与えます。水質が悪いと、すぐに株が腐ってしまいます。
肥料
肥料は、秋に植えつけてから冬になるまでの生育期間中に、集中して施します。主に、液体肥料を規定倍率の1.5倍程度に薄めたものを施します。多くのランとは異なり、春から夏の間は、基本的に肥料は不要です。

病気と害虫
病気:特にありません。
病気は特にありませんが、株元が腐りやすいので、十分注意します。予防としては、風通しをよくし、常に新鮮で冷たい水を与え続けるとよいでしょう。
害虫:特にありません。
用土(鉢植え)
毛足の長い新鮮な水ゴケで植え込みます。乾燥を嫌うので、すぐに乾いてしまう材料は使いません。

植えつけ、 植え替え
プラスチック鉢を用い、水ゴケで植えつけます。毎年花後の秋にていねいに掘り上げ、バルブ(球茎)を分球して、再度植えつけます。鉢内に新鮮な水が行き渡るように、鉢壁にも水抜きの穴をあけておくとよいでしょう。
ふやし方
株分け:株分けでふやすことができます。花後の秋早く、株を鉢からていねいに取り出し、バルブ(球茎)を分球してふやします。
主な作業
下葉取り:枯れてきた下葉は、きれいに取り除きます。そのまま放置すると、株が腐る原因にもなるので、十分注意します。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
一年中、日光を非常に好みますが、夏の高温は苦手です。そのため、夏は日当たりがよくても高温にならない環境をつくらないかぎり、ディサの栽培はできません。
寒さについては、10℃を下回っても大丈夫ですが、極端な低温では株が傷みます。
また、新鮮な風に当たるとよく育ちます。閉めきった環境の場合は、常に換気扇などを回し、空気を循環させる必要があります。

水やり
新鮮で冷たい水を常に与えます。水道水のくみ置き水では、うまく育ちません。山の急流を流れるような、不純物が少なく、手を入れられないぐらい冷たい水を与えます。水質が悪いと、すぐに株が腐ってしまいます。
肥料
肥料は、秋に植えつけてから冬になるまでの生育期間中に、集中して施します。主に、液体肥料を規定倍率の1.5倍程度に薄めたものを施します。多くのランとは異なり、春から夏の間は、基本的に肥料は不要です。

病気と害虫
病気:特にありません。
病気は特にありませんが、株元が腐りやすいので、十分注意します。予防としては、風通しをよくし、常に新鮮で冷たい水を与え続けるとよいでしょう。
害虫:特にありません。
用土(鉢植え)
毛足の長い新鮮な水ゴケで植え込みます。乾燥を嫌うので、すぐに乾いてしまう材料は使いません。

植えつけ、 植え替え
プラスチック鉢を用い、水ゴケで植えつけます。毎年花後の秋にていねいに掘り上げ、バルブ(球茎)を分球して、再度植えつけます。鉢内に新鮮な水が行き渡るように、鉢壁にも水抜きの穴をあけておくとよいでしょう。
ふやし方
株分け:株分けでふやすことができます。花後の秋早く、株を鉢からていねいに取り出し、バルブ(球茎)を分球してふやします。
主な作業
下葉取り:枯れてきた下葉は、きれいに取り除きます。そのまま放置すると、株が腐る原因にもなるので、十分注意します。
0
0
文章
玲儿
2017年09月24日

セロジネの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
1年を通して日当たりのよい場所で栽培します。北方タイプは4月から10月までは戸外の30%程度の遮光の下で管理します。南方タイプは5月中旬から9月まで戸外で同様の遮光下で栽培します。このほかの季節は室内の窓辺に置き、なるべく長い時間日光に当たるようにします。日当たりが悪いと花つきが悪くなります。
水やり
タイプを問わず水が好きな洋ランです。特に春に新芽が伸び始めてから秋の終わりにバルブが完成するまでは、十分な水やりを行います。真夏日が続き熱帯夜があるようなときは、日中と夕方にたっぷりシャワーもかけておくと夏バテしません。冬も植え込み材料を乾かさないように水やりを行います。

肥料
春に固形の有機質肥料を規定量置き肥し、真夏前まで1か月ごとに取り替えます。緩効性化成肥料でもかまいませんが、効果が長く続くので春に1回置き肥するのみとします。液体肥料も固形肥料と同時に施し始め、9月下旬まで週1回水代わりにたっぷりと施します。
病気と害虫
害虫:ナメクジ
ほとんど病害虫が発生しない洋ランで、新芽の伸び始めと、花芽の伸び始めの時期にナメクジに注意する程度です。

用土(鉢植え)
水ゴケでプラ鉢に植えるのが一般的です。水を好む洋ランですから、植え込み材料が常にしっとりとぬれている状態を保てる植え込み材料を使います。バークと軽石を混ぜたミックスコンポストも使えますが、水ゴケ植えのときよりもしっかりと水を与えないと大きく育ちません。
植えつけ、 植え替え
植え替えは2年に1回程度、春4月ごろに行います。植え替え時期が遅れるとその年の生育が遅れ翌年花をつけない原因にもなるので注意しましょう。植え込む鉢は、2年後には株がはみ出すくらいのやや小さめのものを選びます。

ふやし方
通常、株分けでふやします。適期は植え替え同様4月ごろです。バルブの数がふえ、新芽もふえてきたら行います。株分けをせず、大株に仕立てることも可能です。
主な作業
花茎切り:ほとんどの花が茶色く枯れてきたころ、花茎をつけ根で切ります。種類によっては新芽の中から花茎を伸ばしているものもあるので、新芽の葉先を切らないように注意します。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
1年を通して日当たりのよい場所で栽培します。北方タイプは4月から10月までは戸外の30%程度の遮光の下で管理します。南方タイプは5月中旬から9月まで戸外で同様の遮光下で栽培します。このほかの季節は室内の窓辺に置き、なるべく長い時間日光に当たるようにします。日当たりが悪いと花つきが悪くなります。
水やり
タイプを問わず水が好きな洋ランです。特に春に新芽が伸び始めてから秋の終わりにバルブが完成するまでは、十分な水やりを行います。真夏日が続き熱帯夜があるようなときは、日中と夕方にたっぷりシャワーもかけておくと夏バテしません。冬も植え込み材料を乾かさないように水やりを行います。

肥料
春に固形の有機質肥料を規定量置き肥し、真夏前まで1か月ごとに取り替えます。緩効性化成肥料でもかまいませんが、効果が長く続くので春に1回置き肥するのみとします。液体肥料も固形肥料と同時に施し始め、9月下旬まで週1回水代わりにたっぷりと施します。
病気と害虫
害虫:ナメクジ
ほとんど病害虫が発生しない洋ランで、新芽の伸び始めと、花芽の伸び始めの時期にナメクジに注意する程度です。

用土(鉢植え)
水ゴケでプラ鉢に植えるのが一般的です。水を好む洋ランですから、植え込み材料が常にしっとりとぬれている状態を保てる植え込み材料を使います。バークと軽石を混ぜたミックスコンポストも使えますが、水ゴケ植えのときよりもしっかりと水を与えないと大きく育ちません。
植えつけ、 植え替え
植え替えは2年に1回程度、春4月ごろに行います。植え替え時期が遅れるとその年の生育が遅れ翌年花をつけない原因にもなるので注意しましょう。植え込む鉢は、2年後には株がはみ出すくらいのやや小さめのものを選びます。

ふやし方
通常、株分けでふやします。適期は植え替え同様4月ごろです。バルブの数がふえ、新芽もふえてきたら行います。株分けをせず、大株に仕立てることも可能です。
主な作業
花茎切り:ほとんどの花が茶色く枯れてきたころ、花茎をつけ根で切ります。種類によっては新芽の中から花茎を伸ばしているものもあるので、新芽の葉先を切らないように注意します。
0
0
文章
玲儿
2017年09月24日

シンビジウム(シンビジューム)の育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
年間を通して日当たりがよく、より長く日光に当たる場所で栽培します。真冬以外は戸外での栽培が適します。5月上旬から9月上旬は遮光率の低い遮光ネットなどを張り、強い日ざしを避けるようにします。庭木の下などは、明るいようでも日光不足になりがちなので注意が必要です。また風通しも大切で、常に風で葉が揺れている状態が最適です。理想的な状態にできるだけ近づけるように、株どうしの間隔をあけて風が抜けるようにします。冬、室内に取り込んでいるときも、暖かな日中は少し外気に当てるようにするとよいでしょう。

水やり
根が十分張った株は水分をたくさん必要としています。春に新芽を出してから秋にバルブが大きく太って完成するまでは、乾かさないようにたっぷり与えます。特に夏は毎日十分な水を与えます。秋から冬にかけては週1~2回程度の水やりで十分ですが、蕾が伸び始めたら水やりの回数をふやし、水切れさせないようにします。
肥料
春から真夏前まで、固形の有機質肥料を規定量置き肥し、1か月ごとに取り替えます。緩効性化成肥料を用いる場合は、効果が長く続くので春に1回だけ施します。また、液体肥料も同時に施し始めて、9月下旬まで週1回水代わりにたっぷりと施します。

病気と害虫
病気:ウイルス病
葉にまだらの黒い斑点が不規則に出て、花が咲きにくくなります。ウイルス病にかかると治らないので、発見しだい廃棄処分にします。早期に発見して対処しないと周囲の株にもうつるので注意しましょう。
害虫:アブラムシ、カイガラムシ
蕾が大きくなってきたときにアブラムシがよく発生します。また、株が込んでいると葉裏にカイガラムシも発生します。風通しがよくなるように鉢を置き直しましょう。
用土(鉢植え)
ミックスコンポスト(バーク、軽石などを混合したもの)やバーク単体で、プラスチック鉢や陶器の化粧鉢などに植え込みます。苗のうちは細かいものを使いますが、成株になったら中粒の植え込み材料で植えます。鹿沼土などは最初は問題なく育つように見えますが、その後根が腐りやすいので、土系の材料は使わないようにします。

植えつけ、 植え替え
植え替えの適期は春、4月ごろです。2年に1回程度行います。植え込む鉢は、2年後には株がはみ出すくらいのやや小さめの鉢を選びます。植え替え時期が遅れると、その年の生育が遅れ翌年花をつけない原因にもなるので注意します。
ふやし方
通常、バルブの数がふえ、新芽もふえてきたら株分けでふやします。適期は植え替え同様4月ごろです。株分けせずに大株に仕立てることも可能です。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
年間を通して日当たりがよく、より長く日光に当たる場所で栽培します。真冬以外は戸外での栽培が適します。5月上旬から9月上旬は遮光率の低い遮光ネットなどを張り、強い日ざしを避けるようにします。庭木の下などは、明るいようでも日光不足になりがちなので注意が必要です。また風通しも大切で、常に風で葉が揺れている状態が最適です。理想的な状態にできるだけ近づけるように、株どうしの間隔をあけて風が抜けるようにします。冬、室内に取り込んでいるときも、暖かな日中は少し外気に当てるようにするとよいでしょう。

水やり
根が十分張った株は水分をたくさん必要としています。春に新芽を出してから秋にバルブが大きく太って完成するまでは、乾かさないようにたっぷり与えます。特に夏は毎日十分な水を与えます。秋から冬にかけては週1~2回程度の水やりで十分ですが、蕾が伸び始めたら水やりの回数をふやし、水切れさせないようにします。
肥料
春から真夏前まで、固形の有機質肥料を規定量置き肥し、1か月ごとに取り替えます。緩効性化成肥料を用いる場合は、効果が長く続くので春に1回だけ施します。また、液体肥料も同時に施し始めて、9月下旬まで週1回水代わりにたっぷりと施します。

病気と害虫
病気:ウイルス病
葉にまだらの黒い斑点が不規則に出て、花が咲きにくくなります。ウイルス病にかかると治らないので、発見しだい廃棄処分にします。早期に発見して対処しないと周囲の株にもうつるので注意しましょう。
害虫:アブラムシ、カイガラムシ
蕾が大きくなってきたときにアブラムシがよく発生します。また、株が込んでいると葉裏にカイガラムシも発生します。風通しがよくなるように鉢を置き直しましょう。
用土(鉢植え)
ミックスコンポスト(バーク、軽石などを混合したもの)やバーク単体で、プラスチック鉢や陶器の化粧鉢などに植え込みます。苗のうちは細かいものを使いますが、成株になったら中粒の植え込み材料で植えます。鹿沼土などは最初は問題なく育つように見えますが、その後根が腐りやすいので、土系の材料は使わないようにします。

植えつけ、 植え替え
植え替えの適期は春、4月ごろです。2年に1回程度行います。植え込む鉢は、2年後には株がはみ出すくらいのやや小さめの鉢を選びます。植え替え時期が遅れると、その年の生育が遅れ翌年花をつけない原因にもなるので注意します。
ふやし方
通常、バルブの数がふえ、新芽もふえてきたら株分けでふやします。適期は植え替え同様4月ごろです。株分けせずに大株に仕立てることも可能です。
0
0