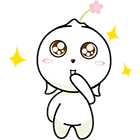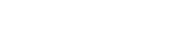花园里是空的哦~
还没有添加花。
动态 (854)
笼岛 みどり
2017年05月28日


目次 #トックリラン の基本情報 トックリランの育て方 トックリランの育て方 まとめ トックリランのその他色々 トックリランの基本情報 徳利(トックリ)のようにふくらんだ株がユニーク。長い葉が頂点から馬のしっぽのようにひろがることから、英名「ポニーテールパーム」でも呼ばれています(単に縮めてポニーテールとも)。パームと付いていますがヤシの仲間ではありません。旧学名の「ノリナ」でもよく見かけます。 原産地では10m以上に成長しますが、日本では鉢植えの観葉植物として流通しています。太い株の中には水分がたくわえられています。そのためトックリランは乾燥に強く、多少水やりを忘れてしまっても元気です。暑さ寒さに強いので、観葉植物の中でも育てやすい品種といえるでしょう。 トックリランの花言葉 樹齢10年を過ぎてからようやく花をつけるようになります。開花は不定期で数年から数十年空くことも。年間通じてトックリランを屋外で育てられる沖縄諸島では、開花が地方紙のニュースになることもあります。福井県では育て始めて60年経った株が初開花したケースも。 細く伸びた花茎の先端に、小さな透明感のあるクリーム色の花がまとまってつくことから「多くの才能」という花言葉があります。生涯に一度は才能たちの集う場面を目の当たりにしたいものです。 トックリランの基本情報科・属キジカクシ科トックリラン属、またはリュウゼツラン科ノリナ属英名Ponytail palm学名Beaucarnea recurvata原産地メキシコ出回り時期通年育てやすさ★★★★☆ トックリランの種類・品種 流通しているトックリランのほとんどが「ボーカルニア・レクルバータ」です。ほとんど同じ外見の「ボーカルニア・グアテマレンシス」も流通しており、こちらの方が移植に強いとされています。

トックリランの育て方用土 水はけのよい土を好みます。赤玉土5に対し川砂は3と多めに。後は腐葉土と堆肥です。市販の「観葉植物の土」は水はけに優れているのでおすすめです。 種まき 適期は5月~7月ですが、種はあまり流通していません。自家採取する場合は大きな株に育てる必要があります。 苗の選び方 葉数が多く、徳利の部分が太く成長している苗を選びましょう。若い苗は購入後、積極的に日に当てるようにします。 植え替え 植え替えはなるべく暖かい時期に。鉢底から根が見えてきたら植え替えの時期。軽く土を落としてから鉢増しします。 水やり 4月~10月は表土が乾いたらたっぷりと。乾燥につよいので、秋冬は乾いてからさらに数日おいて与えます。 追肥 あまり肥料分を必要としません。生育期の4月~10月に遅効性肥料を与えます。液肥なら月2~3回が目安です。 剪定 特に必要ありません。葉が伸びるのに数ヵ月かかるので不用意な剪定に注意します。茶色く枯れた下部の葉は目立つのでカットしてしまいましょう。 病害虫 夏場のハダニに注意しましょう。水でふき取るか、薬剤を散布します。ハダニは水を嫌うので、霧吹きで葉水することによりある程度防げます。 ハダニ ハダニは気温が高いところや乾燥している場所に発生します。暖かい時期に発生しやすく植物の葉から栄養を吸収して弱らせます。また、弱った植物はハダニの被害に遭いやすく、被害も大きくなりやすいです。数が増えて被害が大きくなってくると、葉緑素の不足によって光合成ができなくなり、生長不良になったり、植物自体が枯れていきます。 トックリランの育て方 まとめ ・日光を好み、直射光も平気です。日照量が足りないと葉色が薄くなってしまいます。 ・日差しの向きへ幹を曲げていくので、時々鉢を回転させましょう。 ・耐寒性に優れていますが、寒風が吹きつけたり、氷点下になる時は室内へ。

トックリランのその他色々巨木のトックリランを見るなら 筑波実験植物園では高さ約6mのトックリランが育てられています。もちろん地植え。数年に一度、花をつけることもあります。 同園では日本の植生だけでなく、熱帯雨林など世界の植物相が再現されています。絶滅危惧種の収集に力を注いでおり、乱獲などによってほとんど自生株が見られなくなった「キバナシュスラン」など国産のらんも大切に育てられています。 洋らんを含めた同園のらんコレクションは実に3000種以上。毎冬、「つくば蘭展」が開催されています。 大胆な切り戻しもOK 長くつややかな葉が、馬のしっぽ(ポニーテール)にようによく茂っているのが理想の形。ですが株によっては葉の間が間延びして、だらしなく見えてしまっているものも。そんな時は思い切ってすべての葉を落としてしまいます。 暖かい時期、徳利の首にあたる部分から上をスッパリとカット。数ヵ月には株のあちこちから新芽が出てきます。株の中ほどから伸びたものは樹形が乱れるので再びカット。上部の新芽だけ残します。新芽はたっぷり日に当てましょう。 らんと呼ばれる理由 かつてはリュウゼツラン科として扱われることの多かったトックリラン。現在はキジカクシ科とするのが主流ですが、どちらもいわゆる「らん」の仲間ではありません。ではトックリランもリュウゼツランもなぜ「らん」の名がついているのでしょう? 明治時代まで日本では洋来の珍しい植物に、なんでも「らん」と付けてしまう習慣がありました。メキシコからヨーロッパを経て渡ってきたトックリランもそのひとつです。他にスズラン(キジカクシ科)、チャラン(センリョウ科)、ハラン(キジカクシ科)もやはり珍しさゆえに、らんの名前が付けられてしまいました。

花・植物を、もっと楽しみたい!!室内で楽しもう!花・植物を楽しむインドア編では、観葉植物、インテリアグリーン、インテリアや雑貨など主に室内で楽しめる情報をまとめました。 室内の観葉植物をオシャレに飾ったり、100均DIYでインテリアをつくるアイデアから植物を育てている上でのトラブルや病害虫の対策などなど盛りだくさん。 屋外で楽しもう! 花・植物を楽しむアウトドア編では、庭やガーデニング、玄関・ポーチのアレンジやベランダなど主に屋外で楽しめる情報をまとめました。 こんな素敵なガーデンにしたい!といったアイデア、アレンジから害虫が出てて困っている、庭木の剪定はどうしたらいいの?といった悩みなど盛りだくさん。
文章
笼岛 みどり
2017年05月28日


目次 #万年青 (おもと)の基本情報 万年青(おもと)の育て方 万年青(おもと)の育て方 まとめ 万年青(おもと)のその他色々 万年青(おもと)の基本情報 万年青(おもと)は日本で古くから、主に青々とした葉を観賞する目的で育成されてきた植物です。江戸時代から続く品種改良によって多彩な葉の形状、模様が生まれ、「葉芸」と呼ばれます。品種改良の技術が「芸」として高く評価されているのは万年青だけでしょう。多年草で葉を落とさないことから、長寿を象徴する縁起物として大切にされてきました。「縁起草」「辛抱草」の別名もあります。乾燥も過湿も嫌うので水やりに少々コツが必要ですが、覚えてしまえば基本的には育てやすく丈夫です。寒さに弱いので鉢植えは冬場、室内で管理します。 万年青(おもと)の花言葉 一年を通じて青々と葉を茂らせ、丈夫で生命力にあふれたイメージから「長寿」「長命」といった花言葉がつけられています。実も万年青の鑑賞ポイントです。可愛らしい赤い実が青い葉に包まれている姿は、赤子を抱く母親のよう。そこで「母性愛」「崇高な精神」の意味合いもあります。徳川家康が江戸城に入城する際に万年青を持ち込み、以後長きにわたって将軍家を維持できた逸話にちなみ、「相続」の花言葉もあります。また、1月24日の誕生花になっています。 万年青(おもと)の基本情報科・属ユリ科オモト属英名Rohdea japonica学名Rohdea japonica Roth原産地日本、中国出回り時期通年育てやすさ★★★☆☆ 万年青(おもと)の種類・品種 葉の長さや形によってカテゴリー分けされています。30cm以上の大型の葉を持つものは「大葉系」「大葉万年青」と呼ばれます。代表的な品種に「曙」「大観」があります。20cm程度のものは「中葉系」。さらに葉の形状によって薄い「薄葉系」、厚みのある「縞甲系」、先端のカールする「獅子系」に分類されます。5~10cmほどの「小葉系」は表面の細かいしわが特徴です。

万年青(おもと)の育て方用土 水はけのよい土を好みます。赤玉土ではなく、粒の崩れにくい日向土に、富士砂(溶岩砂)や川砂を混ぜ込んだものを用意します。 種まき 種は管理が難しいため、通常は苗から育てます。品種改良を目指す時は種から育ててみましょう。発芽まで約3ヵ月かかるので、その間は水を切らさないようにします。 苗の選び方 なるべく大きめの苗を選ぶと育てやすさが違います。根を確認できるなら、長く伸びているものを選びましょう。 植え付け 直射日光、西日を嫌うので、午前中だけ日のあたる場所を選びます。鉢植えの場合は水苔を置いて乾燥を防ぎます。 水やり 乾燥を苦手とする一方、過湿も嫌うやや難しい面があります。春秋は毎日、夏は2~3日に一度、冬は4~5日と季節によって表土の様子を見ながらペースを変えます。 追肥 与えすぎは逆効果。春と秋に薄めの液肥をやるだけで充分です。葉の成長が目的なので、油かすを少量与えてもよいでしょう。 剪定 剪定はほとんど必要としません。先端まで変色した古い葉を取り除く程度です。葉が垂れているのは日照不足のサインです。 病害虫 葉を食害するハムシやアザミウマに注意。初夏から夏にかけて殺虫剤をまいて予防しましょう。病気の原因になるので、葉についた水滴はふき取っておきます。 万年青(おもと)の育て方 まとめ ・自然化では木漏れ日の下で育つため、直射日光が苦手です。 ・葉に付いた水滴から雑菌が沸き、病気になることも。葉のしずくはこまめにふき取りましょう。普段から布で表面のほこりをぬぐっておくと、葉のつやを維持できます。 ・植え替えはよく根を伸ばす春か秋に。鉢は植え替えたら鉢ごとバケツに入れ、たっぷり水を与えます。庭植えの場合でも3~4年に一度は用土を取り換えます。 ・寒さは苦手。冬場、5度以下に下がる場所では鉢を屋内に移動させましょう。

万年青(おもと)のその他色々家康と万年青(おもと) 1590年8月1日、徳川家康は豊臣秀吉の命により拠点を江戸城に移します。この時、家臣・長島長兵衛から献上された万年青を3株、城に持ち込みました。葉に斑の入ったこの万年青を、家康は大切に床の間に飾っておいたそうです。江戸入城から10年後、家康は関ヶ原の戦いを制し天下統一。200年以上にわたる徳川幕府を築きました。以来、万年青は長きにわたる繁栄をもたらすと信じられるようになったのです。居城を移した故事にちなみ、現在でも万年青は引っ越し祝いに用いられています。 江戸時代の大ブーム 江戸時代に入ると万年青の品種改良が盛んになり、人気の苗は高額で取引されるまでになりました。江戸後期、国学者の栗原信充は長生舎主人という筆名で『金生樹譜』を上梓します。「金生樹」とは字の通り「金を生み出す樹」。万年青や南天、フクジュソウ、ソテツ、タチバナなどを中心に、高値で売れる苗の育て方を指南したものです。土作りや肥料、鉢の解説、接ぎ木の方法や、室(むろ)と呼ばれる温室での栽培方法も記されており、当時の園芸技術の高さに驚かされます。 万年青(おもと)の種 苗や株分けから育てるより難易度は高めですが、種まきにもぜひチャレンジしてみてください。赤い実がついてから1月頃まで収穫せず、寒さにあてておきます(発芽率が上がるといわれています)。採取したら新聞紙で包み、温度差の少ない場所に保管します。乾きすぎても、湿りすぎても種が傷んでしまうので時折チェックしましょう。3月~4月、水に漬けてから果肉を取り除き、少し尖った発芽点が横向きになるようにしてまきます。
文章