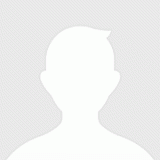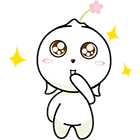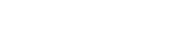求助
666
2017年09月20日

求助 品种名称 有点缀化了 谢谢








0
0
肉~:你这不是缀化,艾伦+2,长得不好
小馒头331:艾伦+1
少女小高:没有缀化啊 艾伦吧
月-兔:可能是乙女心
666:@木梓鸣 这个之前放室外大盆子里养的 结果前段时间天气原因黑腐了很多 这是为数不多顽强活下来的几颗之一 实在是长得太奇葩了 最关键的是还有点缀化了😂
显示更多
文章
权问薇
2017年09月20日


#玻璃翠 修剪时间与方法:
幼苗生长时期要进行2次至3次摘心,可以促进侧枝的生长,增加开花的数量,使整体株型更加美观。
如果玻璃翠涨势过高,要把所有过高的枝条全部剪去,减少不必要的养分流失,涨势过高的枝条也是徒长造成的,所以没有必要在让它继续生长。
发现有涨势弱或较小的枝条,也要适当的修剪,保留较为健壮的枝条;整株植物过密时,也可把较小的枝条剪下。

花期内,玻璃翠的下半(靠近土壤)部分若有花开出,则要及时的摘掉,不可让它继续保留,这样可以让上半部分的开花数量逐渐增多,花朵陆续开放。
玻璃翠是种多年生的植物,所以在每次开花后,花朵会慢慢的越来越稀疏,这时就要强行把稀疏的花朵全部剪掉,可能有的友友会非常的不舍得,认为已经稀疏了,为什么还要全部剪掉呢?剪掉后再配合合理的施肥,会让玻璃翠下次的开花更加繁盛。

贴心提示
玻璃翠生长速度比较快,涨势也比较旺盛,所以在修剪时不必担心,可以放心大胆的修剪,就算最后修剪的株型不满意,给它一段时间,它就会恢复过来。
0
0
文章
张祥明
2017年09月20日


根部变黑原因:
即使#空气凤梨 对环境的适应力再强,生命力在旺盛,也是会出现一些病害,例如根部发黑,这也是养殖空气凤梨最常见的症状。其变黑的主要原因是浇水过多,有的友友会问,依赖空气生存的植物,何来浇水一说;其实浇水就是给空气凤梨喷水,而喷水量过多,潮湿度过大,就很容易使其根部变黑;

有的友友喜欢给植物配一个非常漂亮的器皿,但这对于空气凤梨来说,犹如把它放进一个封闭的环境中,虽然它不靠根来吸取养分,但时间过长,其根须就会因为呼吸不到新鲜空气而逐渐变黑。
根部变黑后的补救措施:
要将空气凤梨根部变黑的地方全部剪掉,防治其扩散的越来越大。日常浇水(喷水)时,一定要适量,可以用喷雾的方法进行浇水,空气凤梨不是靠根部来吸取养分的,而是靠叶片,所在浇水量过大时,叶子便无法在吸取,便导致根部发黑腐烂。
空气凤梨并不适合在器皿中养殖,可以直接放在花架上养殖。同样发现发黑后首先要将其剪掉。

0
0
文章
巴黎铁塔
2017年09月20日


水分不合理
一般情况下,#观音竹 的新生叶子淡黄没有光泽,而老的叶片没有变化,枝干萎缩,长势不佳,这种现象可能是因为浇水比较多造成的。这时要将观音竹从盆土中挖出,放到通风较好的地方,使土壤变得干燥后再重新入盆。

缺水
这种情况一般表现为叶片的边缘出现干枯的症状,叶片有的还会掉落,很明显的就会知道是因为缺水的原因造成的,所以,我们要迅速的补充水分,让土壤时刻保持湿润的状态。
光照不合理
如果将观音竹放在强光下照射,就会出现叶片的边缘和枝条变得萎缩,被照射的部位会出现黄色的斑点,这种情况可以将观音竹转移到室内阴凉的环境就可以了。

缺光
如果长期将观音竹放在阴暗无光的角落,就会导致叶子得不到光合作用,时间长了叶子就会变黄随后掉落,因此,我们需要按时的将观音竹挪到光照良好的环境下,补充生长所需的光照。

施肥不合理
管理观音竹的时候,在其生长旺盛阶段难免会出现使用肥料过盛太浓的现象,从而引起了新生叶片的暗黄,看起来十分的没用光泽。这时就需要停止后续肥料的使用了,并通过浇水的方式来稀释过多的肥料。
0
2
文章
八公
2017年09月20日


病害防治方法:
#茎腐病 的防治方法:建议放在有阳光的温室内养殖,夏天要格外注意其通风,因夏季相对潮湿,而且还比较闷热,对植物的生长很不利;但若发现此病害时,可以用专用药剂进行喷杀,约10天喷一次,喷2次至3次即可。若严重时,要整株销毁。
疫病的防治方法:若在室外养殖,要进行避雨措施,而且还要防止其湿气过重,这都是引发此病害的因素,但若发现此病害时,同样要可以用专用药剂进行喷杀。

炭疽病的防治方法:在植物的生长旺季,约20天至30天施肥一次,可以有效降低此病害的发生。但若发现此病害时,同样要可以用专用药剂进行喷杀。
灰霉病的防治方法:在栽种时就要注意其生长环境,要保持土壤的潮湿度,充足的光线,良好的通风,而且冬季温度必须在16度以上,这样可以有效的减少此病害的发生,但若发现此病害时,同样要可以用专用药剂进行喷杀。

虫害防治方法:
蔗扁蛾(香蕉蛾)的防治方法:在选购植物时,就要细心观察,挑选无病害的健康植物,从源头先杜绝。若发现此病害,可以用专用药剂进行喷杀。
对粒材小蠹的防治方法:此虫害会大多都在生长期发生,一经发现要连续用药物喷杀4次至5次,每隔7天至10天一次。

0
0
文章
玲儿
2017年09月20日

マロウの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
日当たりと風通し、水はけのよい場所が適しています。植えつけ場所や用土に、堆肥や腐葉土などの有機物を十分に加えて植えつけます。
水やり
庭植えの場合は、根が張ったあとはほとんど必要ありません。鉢植えの場合は、鉢土の表面がよく乾いたらたっぷり水やりします。
肥料
元肥として緩効性化成肥料を施します。多肥にすると倒れやすくなるので注意しましょう。成長の始まる春と秋に、追肥として緩効性肥料を置き肥するか、液体肥料を施します。

病気と害虫
害虫:ハマキムシ、アブラムシ、ワタノメイガなど
ハマキムシはハマキガ類の幼虫のことで、葉を巻いたり、つづり合わせたりして、その中にいます。巻いた葉の上から押しつぶすか、葉を開いて幼虫を捕殺します。
アブラムシは、春の成長期に葉や新芽によく発生します。見つけしだい駆除しましょう。数が少ないうちならつぶして退治します。
ワタノメイガは、幼虫が葉や枝を糸でつづって巣をつくり、葉を食害します。葉の上にふんが落ちているのを見つけたら、幼虫を探して捕殺します。幼虫は比較的機敏に動くので、取り逃がさないようにします。

用土(鉢植え)
水はけと通気性に富み、適度な保水性のある土が適しています。赤玉土小粒5、腐葉土3、軽石2などの割合で配合したものがよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
3月上旬から5月上旬と9月下旬から11月上旬ごろに行います。苗を鉢植えにする場合は、太い根を切らないように注意し、9~10号鉢に植えつけます。庭植えでは株間を50~100cmくらいとります。
植え替えは、鉢植えでは株がいっぱいになったときだけ、株分けを兼ねて行います。庭植えでは植えっぱなしにするのがよいでしょう。

ふやし方
株分けやタネをまいてふやします。
株分け:株分けは、大株になったら行います。地上部が枯れた10月から11月に株を掘り上げ、1株に3~5芽つくように、ハサミを入れて株を割ります。
タネまき:4月から6月か、9月に行います。直根性で移植を嫌うので、直まきかポットまきとし、本葉が3~4枚になったら定植します。こぼれダネでもよくふえるので、周囲に発芽した苗を鉢上げしてもよいでしょう。
主な作業
花がら摘み:咲き終わった花は随時摘み取り、花茎の花全体がほぼ咲き終わったら、花茎の根元で切り戻します。花をハーブとして利用する際は、咲いた日に1輪ずつ摘み取ります。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
日当たりと風通し、水はけのよい場所が適しています。植えつけ場所や用土に、堆肥や腐葉土などの有機物を十分に加えて植えつけます。
水やり
庭植えの場合は、根が張ったあとはほとんど必要ありません。鉢植えの場合は、鉢土の表面がよく乾いたらたっぷり水やりします。
肥料
元肥として緩効性化成肥料を施します。多肥にすると倒れやすくなるので注意しましょう。成長の始まる春と秋に、追肥として緩効性肥料を置き肥するか、液体肥料を施します。

病気と害虫
害虫:ハマキムシ、アブラムシ、ワタノメイガなど
ハマキムシはハマキガ類の幼虫のことで、葉を巻いたり、つづり合わせたりして、その中にいます。巻いた葉の上から押しつぶすか、葉を開いて幼虫を捕殺します。
アブラムシは、春の成長期に葉や新芽によく発生します。見つけしだい駆除しましょう。数が少ないうちならつぶして退治します。
ワタノメイガは、幼虫が葉や枝を糸でつづって巣をつくり、葉を食害します。葉の上にふんが落ちているのを見つけたら、幼虫を探して捕殺します。幼虫は比較的機敏に動くので、取り逃がさないようにします。

用土(鉢植え)
水はけと通気性に富み、適度な保水性のある土が適しています。赤玉土小粒5、腐葉土3、軽石2などの割合で配合したものがよいでしょう。
植えつけ、 植え替え
3月上旬から5月上旬と9月下旬から11月上旬ごろに行います。苗を鉢植えにする場合は、太い根を切らないように注意し、9~10号鉢に植えつけます。庭植えでは株間を50~100cmくらいとります。
植え替えは、鉢植えでは株がいっぱいになったときだけ、株分けを兼ねて行います。庭植えでは植えっぱなしにするのがよいでしょう。

ふやし方
株分けやタネをまいてふやします。
株分け:株分けは、大株になったら行います。地上部が枯れた10月から11月に株を掘り上げ、1株に3~5芽つくように、ハサミを入れて株を割ります。
タネまき:4月から6月か、9月に行います。直根性で移植を嫌うので、直まきかポットまきとし、本葉が3~4枚になったら定植します。こぼれダネでもよくふえるので、周囲に発芽した苗を鉢上げしてもよいでしょう。
主な作業
花がら摘み:咲き終わった花は随時摘み取り、花茎の花全体がほぼ咲き終わったら、花茎の根元で切り戻します。花をハーブとして利用する際は、咲いた日に1輪ずつ摘み取ります。
0
0
文章
玲儿
2017年09月19日

ヘレボルス・ニゲルの基本情報
学名:Helleborus niger
その他の名前:クリスマスローズ
科名 / 属名:キンポウゲ科 / クリスマスローズ属(ヘレボルス属)
特徴
ヘレボルス・ニゲルは有茎種(立ち上がった茎に葉をつけ、頂部に花を咲かせる)のクリスマスローズです。常緑の多年草で、清楚な白い花を横向きに咲かせます。葉はやや肉厚です。有茎種として扱われていますが、有茎種と無茎種の両方の特徴や性質をもち、中間種として扱われることもあります。種小名の「ニゲル」は、黒を意味し、根が黒いことに由来しています。
本来、「クリスマスローズ(christmas rose)」はヘレボルス・ニゲルの英名ですが、日本ではヘレボルス属全体をクリスマスローズと呼んでいます。12月に開花し始める早咲きのものもありますが、多くはクリスマスには咲かず、1月になってから開花します。蕾を包む苞葉(ほうよう)がないので、蕾のうちから白い花弁を確認できるのが特徴です。咲き進むにつれてややピンクに色づきます。八重咲きや半八重咲きの園芸品種があります。

主な交雑種に、ヘレボルス・リビダス(Helleborus lividus)と交雑させたヘレボルス・バラーディアエ(H. × ballardiae)、ヘレボルス・ステルニー(H. × sternii)と交雑させたヘレボルス・エリックスミシー(H. × ericsmithii)、ヘレボルス・アーグチフォリウス(H. argutifolius)と交雑させたヘレボルス・ニゲルコルス(H. × nigercors)があります。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
庭植えの場合は、水はけのよい、明るい半日陰に植えつけます。高温多湿を嫌うので、できるだけ涼しい場所を選びましょう。秋から春までは日がよく当たる、落葉樹の木陰などが最適です。
鉢植えの場合は、10月から4月ごろまでは日当たりのよい場所で、5月から9月ごろまでは明るい半日陰で管理します。過湿を避けるため、梅雨どきや秋の長雨には当てないようにしましょう。

水やり
庭植えの場合は、基本的に水やりは必要ありません。
鉢植えの場合は、10月から5月までは、鉢土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。6月から9月まではやや乾かし気味に管理します。
肥料
庭植えの場合は、10月に緩効性肥料を施します。鉢植えの場合は、10月、12月、2月に緩効性肥料を施すほか、10月から4月まで液体肥料を月に2~3回施しましょう。
病気と害虫
病気:灰色かび病、立枯病、べと病、軟腐病、黒斑細菌病、モザイク病など
多くの病気は過湿になったり、蒸れたりすると発生しやすくなります。
害虫:ハモグリバエ、ハマキムシ、ナメクジ、ヨトウムシ、アブラムシ、アザミウマ、ハダニなど
多くの害虫は主に春から秋に発生します。
用土(鉢植え)
水はけ、水もちのよい用土(例:赤玉土小粒4、軽石小粒3、腐葉土3の配合土など)で植えつけます。

植えつけ、 植え替え
適期は10月から12月ですが、10月から翌年3月まで行うことができます。毎年、一回り大きな鉢に植え替えましょう。秋に入手した場合は、根を完全にほぐして古い用土と傷んだ根を取り除いてから植えつけます。冬から春に入手した場合は、根を傷めると生育が悪くなるおそれがあるので、軽くほぐす程度にします。根の数がやや少なく折れやすいので、できるだけ傷つけないように注意して植え替えを行ってください。
ふやし方
株分け:適期は10月から12月ですが、11月から翌年3月まで行うことができます。あまり細かく分けると株分け後の生育が悪くなるので、少なくとも3芽以上つくように分けましょう。
タネまき:5月から6月に熟したタネを採取してすぐにまくか、乾燥させないように秋まで保存して10月にまきます。

主な作業
花がら摘み:花後も花がらを観賞できますが、汚れて見苦しくなり始めたら、株元から切り取ります。タネをとる場合は、タネが成熟するのを待って、花柄を切り取ります。
古葉取り:秋に新芽が展開し始めたら、古い葉をつけ根から切り取ります。枯れた葉や傷んだ葉は見つけしだい、取り除いてください。
学名:Helleborus niger
その他の名前:クリスマスローズ
科名 / 属名:キンポウゲ科 / クリスマスローズ属(ヘレボルス属)
特徴
ヘレボルス・ニゲルは有茎種(立ち上がった茎に葉をつけ、頂部に花を咲かせる)のクリスマスローズです。常緑の多年草で、清楚な白い花を横向きに咲かせます。葉はやや肉厚です。有茎種として扱われていますが、有茎種と無茎種の両方の特徴や性質をもち、中間種として扱われることもあります。種小名の「ニゲル」は、黒を意味し、根が黒いことに由来しています。
本来、「クリスマスローズ(christmas rose)」はヘレボルス・ニゲルの英名ですが、日本ではヘレボルス属全体をクリスマスローズと呼んでいます。12月に開花し始める早咲きのものもありますが、多くはクリスマスには咲かず、1月になってから開花します。蕾を包む苞葉(ほうよう)がないので、蕾のうちから白い花弁を確認できるのが特徴です。咲き進むにつれてややピンクに色づきます。八重咲きや半八重咲きの園芸品種があります。

主な交雑種に、ヘレボルス・リビダス(Helleborus lividus)と交雑させたヘレボルス・バラーディアエ(H. × ballardiae)、ヘレボルス・ステルニー(H. × sternii)と交雑させたヘレボルス・エリックスミシー(H. × ericsmithii)、ヘレボルス・アーグチフォリウス(H. argutifolius)と交雑させたヘレボルス・ニゲルコルス(H. × nigercors)があります。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
庭植えの場合は、水はけのよい、明るい半日陰に植えつけます。高温多湿を嫌うので、できるだけ涼しい場所を選びましょう。秋から春までは日がよく当たる、落葉樹の木陰などが最適です。
鉢植えの場合は、10月から4月ごろまでは日当たりのよい場所で、5月から9月ごろまでは明るい半日陰で管理します。過湿を避けるため、梅雨どきや秋の長雨には当てないようにしましょう。

水やり
庭植えの場合は、基本的に水やりは必要ありません。
鉢植えの場合は、10月から5月までは、鉢土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。6月から9月まではやや乾かし気味に管理します。
肥料
庭植えの場合は、10月に緩効性肥料を施します。鉢植えの場合は、10月、12月、2月に緩効性肥料を施すほか、10月から4月まで液体肥料を月に2~3回施しましょう。
病気と害虫
病気:灰色かび病、立枯病、べと病、軟腐病、黒斑細菌病、モザイク病など
多くの病気は過湿になったり、蒸れたりすると発生しやすくなります。
害虫:ハモグリバエ、ハマキムシ、ナメクジ、ヨトウムシ、アブラムシ、アザミウマ、ハダニなど
多くの害虫は主に春から秋に発生します。
用土(鉢植え)
水はけ、水もちのよい用土(例:赤玉土小粒4、軽石小粒3、腐葉土3の配合土など)で植えつけます。

植えつけ、 植え替え
適期は10月から12月ですが、10月から翌年3月まで行うことができます。毎年、一回り大きな鉢に植え替えましょう。秋に入手した場合は、根を完全にほぐして古い用土と傷んだ根を取り除いてから植えつけます。冬から春に入手した場合は、根を傷めると生育が悪くなるおそれがあるので、軽くほぐす程度にします。根の数がやや少なく折れやすいので、できるだけ傷つけないように注意して植え替えを行ってください。
ふやし方
株分け:適期は10月から12月ですが、11月から翌年3月まで行うことができます。あまり細かく分けると株分け後の生育が悪くなるので、少なくとも3芽以上つくように分けましょう。
タネまき:5月から6月に熟したタネを採取してすぐにまくか、乾燥させないように秋まで保存して10月にまきます。

主な作業
花がら摘み:花後も花がらを観賞できますが、汚れて見苦しくなり始めたら、株元から切り取ります。タネをとる場合は、タネが成熟するのを待って、花柄を切り取ります。
古葉取り:秋に新芽が展開し始めたら、古い葉をつけ根から切り取ります。枯れた葉や傷んだ葉は見つけしだい、取り除いてください。
0
0